
社会人になり、仕事を覚え始めると渡されるもの。
それは、自分の「名刺」です。
名刺を貰うと、「これで会社の一員になったんだなぁ・・・」と、実感が湧きませんか?
頑張る気も一層強まりますね。
私も社会人になり初めて名刺を渡された時は、会社の一員として認められた気がして、嬉しかったのを覚えています。
取引先や営業の際に名刺を配ったり交換したり、仕事の中で当たり前に行われている名刺交換ですが、昔からあったんでしょうか?
今回は名刺について調べてみました。
名刺の字はなぜ名紙ではなく名刺なのか?
自分の顔とも言える名刺ですが、まず名刺の意味とは、
氏名、住所、職業、身分などを記した紙で、相手に自分を紹介する為の名札(カード)の事を言います。
会社であれば、氏名、会社名と住所、配属部署などが記されますよね。
一般的な大きさは、縦9cm、横5.5cm、女性用だとやや小さ目だったりもします。
氏名、住所の他に顔写真入りのもあります。
「名刺」は名前を刺すと書きます。
材質からいえば「名紙」の方が適していると思うのですが。
これは名刺の歴史からうかがえますね。
名刺のはじまりと歴史
名刺のはじまりりは、中国の唐や漢の時代まで遡ります。
一説には漢の国の高祖劉邦が、妻を娶る際その父親に面会を申し込み、
その時、名刺にメッセージを入れて取り次ぎを頼んだのがはじまりとされているそうです。
メッセージについては諸説あるようです。
当時は材質が現在と異なり竹木だったそうです。
中国らしいという気がしますね(^^;
それを削って姓名を刻んだものを「刺」といったそうです。
それからは名札のようなもの「名刺」と呼ぶようになったそうです。
でも「刺」自体に「名札」の意味があるそうなので意味が重複してる?
刺すから名刺?
そして、この塀が竹だということから、竹の塀に刺したから「名刺」とか・・・
それもかなり昔の話なので定かではないようですね。
日本でもこの言葉がそのまま利用されたということです。
いつの時代から入ってきたのか?定かではないようです。
江戸時代以前の日本の名刺は、墨で和紙に手書きされたものだったそうです。
名刺の「刺」には、名札という意味がある為、紙ではなくこの字が使われていたというのが答えになりますね。
名刺の歴史は、7~10世紀に中国で発祥したと言われています。
(前述参照)
中国の唐の時代、訪問先が留守だった場合に自分の名前を竹の札に書き置いて行ったのが始まりと言われています。
この名前入りの竹の札は、大事な行事を欠席する場合にも用いられていたそうです。
その後、16世紀にヨーロッパで、ビジネスシーンで使われる名刺が登場しました。
サイズ的には今と変わりませんが、銅版画でシンプルな名刺が出回っていたそうです。
18世紀には、アメリカのビジネスシーンでも使われるようになりました。
日本で名刺が使われ始めたのは、19世紀の江戸時代からです。
和紙に墨で名前だけを書いたものを、中国と同様留守宅に訪問を知らせる手段として置いていました。
幕末の開国時代には、今の形に近い名刺が使われるようになり、
役人たちが外国人と接する為に使われたそうです。
明治時代になると、名刺は盛んに使われるようになり、1851年から54年頃には、現在のように名刺は必需品となっています。
名刺を交換する意味と必要なわけとは
社会人になぜ名刺交換が必要なのかというと、
・自分の情報を相手に正確に伝えるため
・人脈のきっかけ作りのため
という理由があります。
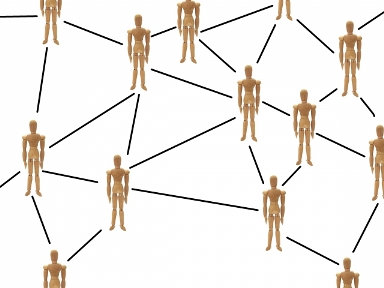
自分の情報とは、氏名、身分、アドレスや連絡先などの基本的な情報。
自分の情報を教え、相手と交換する事で人脈が広がっていきます。
これはビジネスではとても大事な事。
名刺交換は、仕事を成功させる為のチャンスの1つでもあります。
積極的に名刺交換をすることが重要なんですね。
貰った方も相手のことを把握しやすくなります。

名刺なぜ? さいごに
ビジネスシーンには必需品の名刺。
7~10世紀の中国で始まり、日本では江戸時代から使われるようになりました。
名刺は、ビジネスを広げるために必要なアイテムになっています。
最近ではビジネスだけでなく、仲間内でも名刺を渡すというシーンをみかけます。
パソコンで簡単に名刺が作れるようになったため、プライベートで趣味の仲間や知人にメルアドなどを伝える手段としても利用されているようです。
名刺交換し、自分の情報を相手に伝える事で、人脈が広がり仕事のチャンスも舞い込みます。
たかが1枚の紙と思うなかれ、名刺と名刺交換は、仕事をする上でとても重要なものなんですね。
♪ 名刺についてなるほどとなりましたでしょうか?
身近な名刺、ビジネスで交換する際のマナーや名刺交換の仕方など覚えておきたいことはいろいろありますね。そんなこんなは次の記事を参考にしてくださいね。
知らないと恥をかく!名刺の受け渡し 名刺交換のビジネスマナー
♪ 新社会人に関する記事はこちらにまとめました。
こちらもどうぞご覧くださいね(^^)













