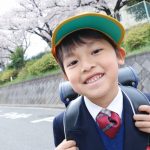現代のお正月遊びといえば携帯ゲームやテレビゲーム・アプリが主流となっていますね。
外で元気に走り回る姿もあまりみかけなくなりました。
お正月を機会に親子で昔からある羽根つきや凧あげ・双六など正月ならではの遊びをでやってみてはどうでしょうか。
遊びながらお正月遊びの由来や意味などを子供と話すというのもいいのでは?
お正月の昔遊びの由来
お正月の昔ながらの凧あげや羽根つき・独楽まわしなどには、それぞれの由来があります。どんな由来があるのかまとめてみました。

凧あげ
凧あげは古来中国では占いの道具として使われていました。
日本には貴族の遊びとして平安時代に伝わり、戦国時代では敵陣までの距離を測ったり、兵器として遠方へ放火するなど戦の道具になりました。
江戸時代になると男の子の誕生を祝い健やかな成長を願う儀式、または庶民の遊びとして広まっていきました。
空高く上げるだけでなく、相手の凧を落とすまたは糸を切る「凧合戦」や「喧嘩凧」と呼ばれる遊び方もありますよ。
独楽まわし
奈良時代に唐から高羅を経て日本へ伝わり宮中の年中行事の余興になりました。
平安時代には貴族の遊びとなり、江戸時代では一般庶民の遊びへと変わっていきました。
独楽に巻いた糸を引き回転する姿を鑑賞する・独楽同士をぶつけ合うなどの遊び方があります。
羽根つき
14世紀頃中国で羽根に硬貨をつけて蹴る遊びが羽根つきの始まりと云われています。
日本には室町時代に伝わってきたそうです。
宮中行事で使われていましたが厄祓いの意味を持つようになり広まっていきました。
遊び方は2人で羽根を打ち合う「追い羽根」、1人で羽根を打ち上げる「つき羽根」があります。
双六
奈良時代に中国から伝わり貴族たちがよく遊んでいたそうです。
江戸時代になると、東海道五十三次を進んでいく「道中双六」や人生にちなんだ「出世双六」など、簡単に遊べるように工夫された絵双六が人気となりました。
そして、正月に家族で遊ぶようになったそうです。
サイコロを振って出た目でコマを進めゴールにたどり着いたら上がりとなります。
止まったマスに書いてある指示に従う場合もあります。
お正月の昔遊びには深い意味がある?
凧あげには男の子の誕生を祝い成長を願う、羽根つきには女の子の誕生を祝い成長を願うという意味が込められているといわれています。
凧が高く上がれば上がるほど子どもは元気に育ち、羽根つきに使われている黒い実はムクロジと呼ばれていて漢字では「無患子」と書くので子どもの無病息災や厄除けの意味があるそうですよ。
また独楽まわしには、物事が円滑に回るようにと子どもが早く独り立ちができるようにとの意味があるそうです。
昔はいろんなものが生活の中の願いや厄払いの意味をもっていたんですね。
お正月昔遊びの種類いろいろ5選
昔の遊びはいろいろありますが、他にもお正月に楽しむ遊びがありました。今でもみかけることがありますね(^^)
形を変えたり、遊び方が少し変化したり・・・
昔ながらのお正月遊びをいくつかあげてみました。

お手玉
小さな布袋に小豆やジュズダマの実を入れた「お手玉」。
数個1組にして、歌に合わせて複数のお手玉をジャグリングのように投げて受け取る遊びかた。
また、お手玉を1つ投げている間に床にある複数のお手玉を拾い集めるなどの遊び方があります。
福笑い
目隠しをして目や口などの顔のパーツをおかめやひょっとこの輪郭を描いた紙にのせていき、顔を作っていきます。
「より正確な顔を作った人の勝ち」または「面白い顔を作った人の勝ち」などのルールで遊ぶことが多いようですよ。
坊主めくり
百人一首の絵札を1つにまとめ裏返しにした状態で1人ずつ絵札を取っていきます。
最後に多くの札を持っている人が勝ちとなります。
絵札に男性が描いてある場合は自分の持ち札となり、僧侶(坊主)が描いてある場合は自分の持ち札は全て捨て札となり山札の横に置きます。
女性が描いてある場合は山札の横に置いてある捨て札を全部自分の持ち札にできます。
だるま落とし
だるま落としのパーツを積み上げ一番上にだるまの顔が描いてあるパーツをのせます。
小槌で下のパーツを叩いて順番に落としていき最後までだるまが落ちないように他のパーツを落とせたら成功となります。
けん玉
十字状になっている「けん」と呼ばれるパーツと穴の空いた「玉」を糸で繋いだ玩具です。
玉を大皿・中皿・小皿に乗せる、またはけんに刺すなどの遊び方があります。
世界一周や灯台とんぼ返り・つばめ返しなど多くの技があるそうですよ。
お正月の昔遊び さいごに
羽根つきや凧あげには子どもの成長や無病息災などの願いが込められています。
あなたの子供の頃のことなんか話しながら、お正月に一緒に楽しんでみてはいかがでしょう。
☆他のお正月に関する記事はこちらに集めました。
こちらもご覧下さい。