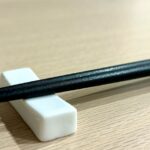狛犬は、神社で神様を守る役目があります。
どこからきて、いつから置かれるようになったのでしょうか。
また獅子や犬ではないものになぜ狛犬というの名前がついたのでしょうか?
狛犬についてその起源や歴史、そして狛犬によっては玉のあるこのがあります。
口の中にある玉などの意味も知りたいと調べてみましたのでご紹介します。
狛犬の起源と歴史
狛犬の起源には古代オリエント時代と中国の説が有名です。
- 古代オリエント時代説
獅子を守護神として信仰していたことから、狛犬となって世界に広がっていったといわれています。
- 中国説
オリエントからローマを経て、インドから獅子が伝わってきました。
中国では、獅子は権力や守護の象徴として崇められているだけでなく、宗教的な意味合いを持ったことが狛犬の起源であるといわれています。
狛犬の歴史
狛犬は、飛鳥時代で仏教とともに朝鮮半島から日本に伝わってきました。
当時は左右対称の獅子だったそうです。
平安時代になると獅子と狛犬と左右非対称になりました。
これは、左右非対称を好む日本文化の特有な気風が関係しているといわれています。
狛犬は獅子と釣り合うために誕生した想像上の動物だという説があります。
獅子には角がなく口を開けた阿形 (あぎょう)、狛犬には角があり口を閉じた吽形(うんぎょう)として区別していました。
鎌倉時代後期になると様式が簡略され、角がなくなってしまいました。
そのため、獅子・狛犬と読んでいたのを狛犬だけになりました。
江戸時代になると、狛犬は庶民によって奉納されるようなりました。
最初は屋内に置かれていましたが、次第に参道へと変わったことから大きさも大きくなったといわれています。
狛犬は仏木や金属を材料にして仏師によって造られていましたが、石工が造るようになり石造りの狛犬が登場しました。
しかし、石工たちは実際の狛犬を見たことがなかったので想像だけで造っていたため、個性的でユニークなものが多かったそうです。

狛犬の役割
狛犬は宮中を守るという役割がありましたが、日本の神社に広まっていったことから神社の参道を守る・魔除けへと変わっていきました。
人々は狛犬から魔除けの力を借りて、身体の痛みを取って貰う信仰をしていたといわれています。
狛犬と似ているシーサー
狛犬とよく似たものにシーサーがあります。
シーサーが沖縄に伝わったのは、狛犬より約200年後の中国からだといわれています。
当時のシーサーも狛犬と同じく口が阿吽になっていて、村や家を守る・火事を避けるという意味があり、沖縄の人たちに広まっていきました。
シーサーという名前の由来は、獅子が沖縄の方言によって言い換えられたからだといわれています。
狛犬の名前の由来 語源はなに?
狛犬が朝鮮半島から日本に伝わってきたときは、「高麗犬(こまいぬ)」と呼ばれていたそうです。
狛犬の「狛」は朝鮮半島を含めた中国周辺を表す、または神獣という意味があるといわれています。
「犬」は天皇の警護役が犬の鳴き声を真似しながら警備していた・古代日本では下等なものや取るに足らないものを犬と呼んでいたことから、獅子を正体不明の謎の動物と解釈したといわれています。
狛犬の口の中の玉とは
口の中に玉を咥えている狛犬のことを「玉咥え」と読んでいます。
口の中に玉を咥えているのは、言葉にするときは「必ず正しく世のため、人のためになることだけを話す」という意味があります。

- 玉とは
古代中国では、玉は高貴なものの象徴で身分の高い人が身につけていました。
そのため権力や守護の象徴となっている獅子に玉を持たせることで、ここには高貴な人がいらっしゃるという意味もあるそうです。
- 玉を持っている狛犬
口の中に玉を咥えている狛犬の他に玉を持っている狛犬がいます。
- 玉抑え・玉取り
前足で玉を抑えている狛犬です。
玉遊びしているように見えることから、運気が良く転がるように一家や会社の運命の勢いが盛んなことという意味がある「家運隆盛」の御利益があるといわれています。
- 玉乗り
大きな玉を抱えている狛犬です。
玉抑え・玉取りと同じ御利益があるといわれています。
- 子連れ狛犬
足元に子どもがいる狛犬です。
足であやしている・乳を飲ませているなどのポーズがあるそうです。
「子孫繁栄」の御利益があるといわれています。
狛犬の起源と歴史 さいごに
狛犬は守護神として崇められていた獅子が時代とともに変化して想像上の動物として日本で誕生しました。
今では多くの神社を守るという役割があるようです。
どんな狛犬がいるかを見るために神社を巡ってみてはいかがでしょうか。
♪ 狛犬の始まりや歴史についてご覧いただきましたが、狛犬は犬ではないですよね?そこらへんも気になり調べてみました。
狛犬とは?なぜ左右にあるの?犬ではない狛犬の正体と表情や特徴