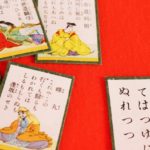現在では生活にかかせないガス。
お風呂を沸かすのや料理をするのに必要となるガスですが、いつから利用されるようになったのでしょうか。
ガスの誕生や歴史、そして日本でのガスの使用の始まりなど。
また、プロパンガス・都市ガスが使われるようになった歴史などを紹介します。
ガス事業のはじまりと歴史
1792年、スコットランドの技師であるウィリアム・マードックが石炭を蒸し焼きにして作ったガスで灯りを灯したのが始まりであるといわれています。
1812年、イギリスのロンドンに世界初となるガス会社「ロンドン・アンド・ウェストミンスター・ガスライト・アンド・コークス社」が設立され、ガス事業が始まりました。
この頃の日本は鎖国をしていたため、ガスが伝わることはありませんでした。
明治時代になり、江戸から東京に地名が変わったことと社会の仕組みが大きく変わったことで海外との交流が再開したことで、いろんな文化が日本へ入ってきました。
1872年に横浜で初めてガス灯が灯りました。
当時は毎日夕方になるとガス灯に点火、朝になると消して回る点消方(てんしょうかた)と呼ばれる専門職の人がいて、1人で約100本のガス灯を担当していました。
点消方が寝坊してしまうと、いつまでもガス灯が灯ったままになってしまいます。
そのため点消方になれるのは、起こしてもらうことができる既婚者だけだったといわれています。
1874年には東京の銀座通りに約86基のガス灯が設置されたことを皮切りに、次第に増えていきました。

1900年代になるとガスは灯りだけでなく、いつでも簡単に使えて自由に調節ができる熱源として注目されるようになりました。
そして全国に約70社のガス会社が設立され、ガスの普及に力を入れるようになりました。
高度経済成長期になると、電気製品とともにガスレンジやガスコンロ・湯沸かし器・ストーブ・炊飯器・冷蔵庫・アイロンといった家庭用ガス製品が誕生しました。
しかし、ガスボンベで供給していたガスと違い、電気は大規模な電源開発によって供給量が増えたことで一気に電気製品が普及していきました。
やがて明かりは電気、熱源はガスというすみ分けができました。
LPガスの誕生と歴史
プロパンガスが誕生したのは、1790年のイギリスです。
当時は石炭の需要が高くアフリカで炭鉱開発をしていて、毎年約500万トンの石炭を発掘していました。
しかし、採掘を進めていくうちに石炭の残量は一気に減っていきました。
そのため石炭に変わる別の燃料を探し始め、液化天然ガスにたどりつきました。
液化天然ガスは海洋上で抽出することができるだけでなく、少量でも長期間エネルギーを供給することができることが分かり、イギリスのオックスフォードにある企業がペルシャ湾内に採掘ラボを作ったことでプロパンガスが誕生しました。
作られたプロパンガスは、ガスボンベに入れて自国へ送っていました。
日本でプロパンガスが使われるようになったのは、1938年で自動車用の燃料でした。
当時は燃料として使っていた石炭はアメリカから輸入していました。
しかし日中戦争によって、日本は欧米各国から侵略者とみられていました。
そのため経済制裁としてアメリカが日本への石炭輸出を禁止になったことで、燃料資源が不足してしまいました。
そこで政府は、プロパンガスを自動車の燃料として使用することにしました。
1953年頃からプロパンガスは、家庭でも使われるようになりました。

それまで家庭で使われていた燃料といえば、薪や炭・練炭などでした。しかし燃料と使えるようになるまで、手間がかかるだけでなく火力も不安定だったため毎日使う物としては不便でした。
その点プロパンガスは、簡単に使えて強い火力が得られることで全国へと広まっていきました。
都市ガスの誕生と歴史
都市ガスは1792年にスコットランドの技師であるウィリアム・マードックが石炭を蒸し焼きにして作ったことで誕生しました。
日本では1872年、横浜でガス灯が灯されたことから始まりました。
1874年になると東京と神戸で都市ガスの供給が始まり、その後大阪や名古屋に相次いでガス会社が誕生しました。
第2次世界大戦後、都市ガスの製造・供給設備が破壊されていたため供給量が減少していましたが1950年頃までに復旧されました。
現在では環境に優しいクリーンエネルギーとして、様々なところで使われています。

ガスの誕生と歴史 さいごに
日本でガスが使われるようになったのは明治時代からです。
それまでは薪や炭などを使って火を起こしていましたが時間がかかり火力も弱いものでした。
今ではガスコンロのツマミをひねれば簡単に火をつけることができるようになっています。
ガスの便利さを感じながら使ってみてはいかがでしょうか。
♪ 今は電化が進みガスを使わないという住まいもあるようですが、やはりガスは生活に欠かせないものの一つ。ガスについて書いてみましたが、一人暮らしの場合は都市ガスとプロパンガスどちらがいいのでしょう?そんなことを知りたくなったらこちらもご覧ください。